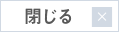監督の松永大司と初めて会ったのは、2011年の春、東日本大震災から一カ月あまりたった頃だった。映画『トイレのピエタ』のスタートはまさにこの時だった。
原発事故の影響で外国人の姿が消えた六本木のカフェで、松永と2時間ほど話をした。私は彼が監督した短編『おとこのこ』をたまたま見る機会があり、その非凡な演出力に興味を持っていた。そこでは素人の中学生がいじめられっ子を非常にリアルに演じており、短い時間の中でも彼らの心情変化がヴィヴィッドに描かれていた。
松永は『ウォーター・ボーイズ』に役者として参加していたこと、高校時代からの友達ピュ〜ぴるのことなどを話してくれた。松永の話は彼の作品同様に面白く、作品と人柄が一致していた。
映画監督として劇場用映画を撮りたいと熱く語る松永に、「どんな映画が撮りたいの?」と質問した。
どんな映画を撮りたいのか?
まだデビューしていない若い監督候補生の人間には必ずする質問だ。自分が何をしたいか分からない人間はゼロからモノを創造するエネルギーを発することはできないし、やりたいことがある場合はそこから出来あがる映画を想像できる。
「手塚治虫さんが病床で書いていた日記の絶筆に“トイレのピエタ”というのがあるんです。NHKの追悼ドキュメンタリーで知ったのですが、それをやりたいです。癌を宣告された男がトイレにピエタ像を書くという、たったそれだけのアイデアですけど」と松永は答えた。
「それは、いいね。可能性がある。とりあえず、プロットを書いて読ませてよ」
私は直感的に、この話は今の自分にとって重要だし、おそらく今の日本にとっても大切な物語になるかもしれないと感じていた。
その頃の私は、自分にも周囲の環境にも行き詰まりを感じ、気力も希望もなくなり抜け殻の状態だった。50歳を目前にして、長く勤め上げた会社を辞めようか悩んでいた。そんなとき、あの震災がおこった。
手塚治虫は「浄化と昇天、これがこの死にかけた人間の世界への挑戦だったのだ!」と最後に記した。100%真実なことが一つある。それは人は確実にいつか死ぬということだ。震災は私にそのことを思い出させた。この世に生を受けたその瞬間からみな、死に向かって走りはじめる定めなのだ。
ではいったいぜんたい、生きるということはどういうことなのだ?
私はこの根源的なテーマに立ち向かいたくなった。萎えていた映画に対しての意欲が湧いてきた。この、結論がでるかどうかわからない大問題を映画にすることが、自分にとって、そしてそれが手塚の言うところの最大の挑戦だった。
松永と私はそれから二人で、脚本をつくり始めた。1年近くたったころ、私はプロデューサーの甘木モリオ氏に声をかけた。オリジナルの脚本で監督が新人という企画に予算的余裕があるわけなかった。彼が厳しい予算管理をするがハートがある男であることは一緒に仕事をしたことがあるからわかっていた。そして、まったくの偶然だったが、彼自身が癌の手術をした直後だった。
ほどなくして私は会社を辞めて独立した。『トイレのピエタ』を作るという目的は、フリーになるという決断をまえに臆病風に吹かれていた私に、少しばかりの勇気を与えてくれた。けっきょく私の場合、映画を作るということが生きるということなのかもしれない。
3年がたち、何度か危機的な状況に直面したが、それを乗り越えここに映画は完成した。この映画に参加した野田洋次郎をはじめとするキャスト、監督をはじめとするスタッフ、出資者のおかげである。
今私はここで、この映画の解題を述べることはしない。それは、「人はなぜ生きているのか?」「生きるとはどういうことか?」といった類いの質問に答えようとするのと同じだ。それは映画を見た各人が答えを見つけてほしい。見て、主人公の宏や真衣や横田の感情を体験してほしい。
画家志望の若い男が癌を宣告されて、トイレにピエタ像を書いて死ぬ―ただ、それだけの話である。しかし、そこには生というものに真摯に向き合った魂の軌跡が刻印されている。宏の最後の夏に現れた真衣は、恋という自覚もないままに、二人だけの魂の交感を経験する。そして、ラストシーン、真衣の絶望が希望へと変わる瞬間を私たちは目撃する。たしかに、宏は生きていた。この作品は最も痛切で純粋なラブ・ストーリーでもあるのだ。
親しい者の死は哀しい。しかしそれは私たち生者の魂を毀損するものではない。死を想うことによってこそ、私たちは今の大切な一日、一日を充実して生きられるはずなのだ。人は他人の生を生きるのではなく、結局、自分自身の生を生きるしかないのだから。
殺伐として先の見えない空気が漂う今という時代だからこそ、そのための勇気をこの映画から少しでも感じとっていただければ幸いである。
2015.1.17
プロデューサー 小川真司